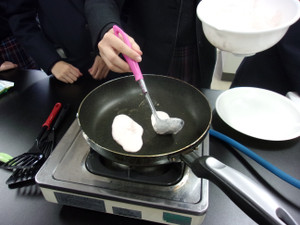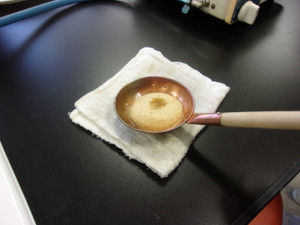野外研究部のひなまつり
3月3日のひなまつりが近づいてきました。
しかし、その日は定期考査中です。
よって、3月になる前に桜餅をつくりました。
昨年の5月に塩漬けにしておいたオオシマザクラの葉を使いました。
白玉粉と小麦粉を混ぜて食紅で色を付けます。
それをフライパンで焼きます。
薄くのばして焼くのがコツです。
焼きあがったらあんこを巻いて、さらにオオシマザクラの葉を巻きつけます。
出来上がりです。
部員たちはそれぞれ自分でつくって食べました。
他の部活の部員もどこからか現れて食べていきました。
みんなでつくって食べているところに、突然悲鳴が。
振り向くと、食紅の入れ物から大量の食紅が床にこぼれていました。
桜餅だけでなく、床まで赤く染めてしまいました。