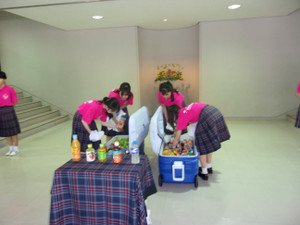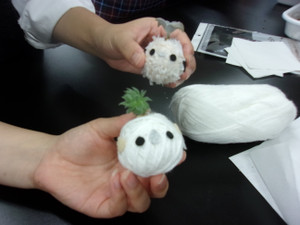クリを使って
先日、クリ拾いをした後、何をつくって食べようか議論したところ、「栗バター炒め」になりました。
「なにそれ?」という部員が多数。
つくり方さえよくわからないまま当日を迎えました。
とりあえず、クリの皮はむいておきました。
40分ほど煮込んでみました。
ほとんどの部員たちはこれから何ができるのかわかっていません。
バターを入れたフライパンにクリを入れ、ベーコンと醤油で味付けをしました。
どのような味になっているのか、この時点では不安しかありませんでした。
でも食べてみると、クリの甘味とベーコンのしょっぱさにバター風味が加わり、今まで体験したことのないおいしさに出会いました。
一口食べた後、おかわりの行列ができました。
クリがたくさんあったので、砂糖でも煮てみました。
こちらも満足できる味でした。
学校のクリがこんなにおいしいと気づかされた活動でした。