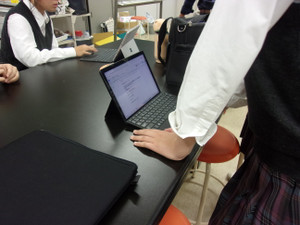2023年12月12日 (火)
2023年12月 6日 (水)
2023年11月18日 (土)
2023年11月16日 (木)
2023年11月14日 (火)
2023年11月 9日 (木)
クリスマスリースづくりを始めました
早いもので12月もすぐそこまで来ています。
そこで、クリスマスに向けてリースづくりを始めました。
今年も学校内に生えている植物を使ってつくりたいと思います。
旧校舎の敷地内にはクズがたくさん生えています。
クズのつるを使って巻いていきます。

初めはちょっと慣れない手つきでした。

巻いていくうちにだんだんと楽しくなってきました。
小さめのリースができました。
リースの大きさはそれぞれです。
大きさや太さは出来上がりをイメージしてつくりました。

太めに巻いてつくったものです。
一般的には厄介者のクズも、このような利用方法があることを知りました。
出来上がるとなぜか頭にのせる部員が多くみられました。