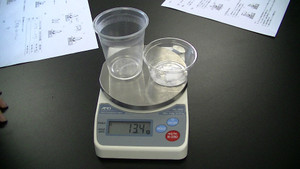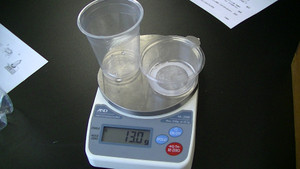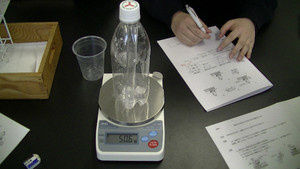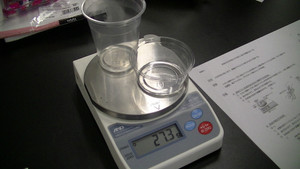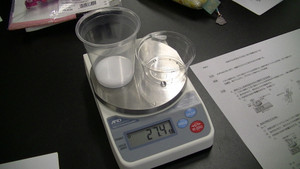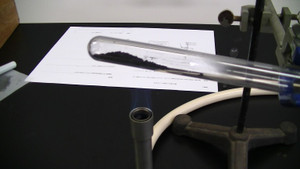2016年1月21日
昨年から暖かい日が続いていましたが、1月中旬になってやっと冬らしくなってきました。
しかし、冬の訪れを感じたと思ったら、前庭の梅が例年よりの2~3週間早く開花してしまいました。
生き物たちはもう春に変わってきているんですね。
今学校では、冬と春の両方を感じることができます。

オオイヌノフグリ
早春の花の代表であるこの花がもう咲き誇っています。
太陽が当たる午前中にたくさんの花をつけますが、花は1日で枯れてしまいます。

えさ探し
何の動物かわかりませんが、雑木林のあちらこちらで動物が掘った穴が見つかります。
この時期はまだ食べ物が少ないので、生きるために必死なのでしょうね。
学校周辺には野生動物がたくさんいます。
キツネ、タヌキ、ハクビシン、アナグマなどがすんでいます。

カラスの足跡
迷惑がられるカラスですが、霜で柔らかくなったグランドに残された足跡を見るとかわいらしさも感じられます。

センダングサ
新しくなかまを増やすため、近くに動物が通らないかと待っているひっつき虫のひとつです。
スカートやズボンのすそにたくさんついてそれを取って捨てた人もいると思いますが、捨てられることでそこに種子が落ち、芽を出すことができるのです。
植物にとってはそれがなかまを増やす作戦なんです。

カシワ
カシワやクヌギなどは冬になっても葉を落とさないことで知られています。
新しい葉が出るまで葉が落ちないことから、古いものから新しいものへと譲られる縁起の良いものとされています。

テイカカズラ
名前は百人一首を選んだ藤原定家からつけられました。
定家が愛する人を忘れられず、この植物になってその人の墓石にからみついたといわれています。

キヅタ
冬になっても枯れずにいるため、今の時期の雑木林では目立っています。
葉はいろいろな形のものがあり、本当に同じ種類なのかと思ってしまうほどです。
葉の形によっては花をつけるものもあるようです。

キノコ
キノコといえば秋ですが、木の幹に半円状にできるサルノコシカケのなかまは、何年もかけて大きくなります。
![]()
![]()
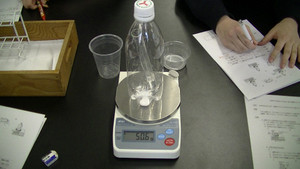
![]()