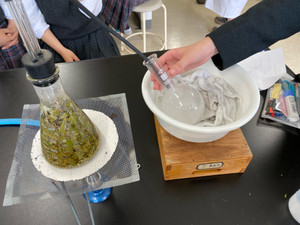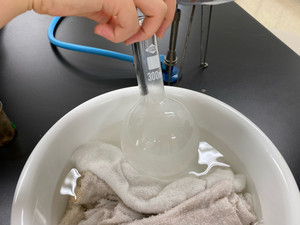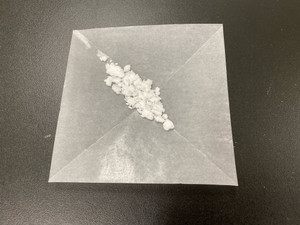共立二中高の自然がいっぱい2 (197)
2022年7月22日
6月下旬に梅雨明けとなり、7月上旬は猛暑日が続きました。
しかし再び梅雨のような日々に戻ってしまい、天気に左右された7月でした。
そのような中、1学期が終了し夏休みとなりました。
夏の学校行事は新型コロナのため中止となったものもありますが、よい経験をたくさんして思い出に残る日々を過ごしてほしいと思います。
クマシデ
前庭でビールの原料となるホップのような実をつけています。
漢字で書くと「四手」と書き、しめ縄などから垂れる白い階段状の紙のことを指します。
それがこの実に似ていることからこのように呼ばれているようです。
ヤマユリ
学校内のあちらこちらで甘いにおいを発しています。
花が重すぎて垂れてしまい、地面についてしまっているものもあります。
このユリが品種改良されて、花屋さんで売っている多くのユリがつくられたようです。
オオバギボウシ
グランドわきの雑木林でひっそりと咲いています。
きれいな花が咲いても誰も気づいてくれません。
たまにサッカー部がボールを拾いに来てくれるくらいです。
ドングリのあかちゃん
秋にはたくさんできるドングリも今は小さな状態です。
これからどんどんと大きく育っていきます。
ヒメヤブラン
この花も雑木林にたくさん咲いているのですが誰も気づいてくれません。
とても小さい花なので、足元をよく見て歩かないと踏んでしまいます。