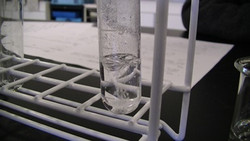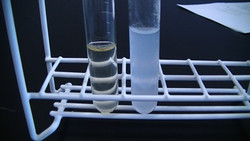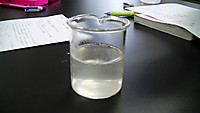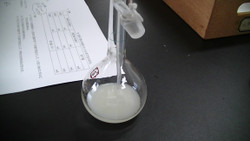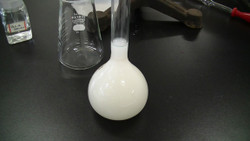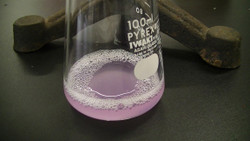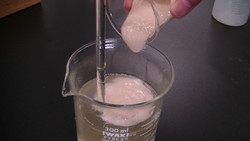高校2年生の理系クラスでは、2学期後半から無機化学分野の学習を始めました。
アルカリ金属は、周期表の1族元素のリチウムLiやナトリウムNa、カリウムKなどをいいます(水素Hは除く)。
また、アルカリ土類金属は、2族元素のカルシウムCaやストロンチウムSrなどをいいます(ベリリウムBe、マグネシウムMgは除く)。
どちらも反応性が大きく、化合物として岩石や海水中に多く存在する元素です。
さて、今回の実験ではナトリウムとカルシウムの単体を用いて、反応性などを調べてみました。
まずはナトリウムの実験から。動画をご覧ください。
ナトリウム①:Na1.wmvをダウンロード
ナトリウムは軟らかい金属で、ナイフで簡単に切ることができます。
表面は酸化されていますが、切り口を見ると銀白色で光沢があることが分かりました。
ナトリウム②:Na2.wmvをダウンロード
水槽に少量のフェノールフタレインを溶かした水を入れておきます。
水面にろ紙を置き、米粒よりやや大きなナトリウム片をその上に置きます。
しばらくすると、水と反応し、黄色い炎をあげて燃焼します。
また、溶けたあとの水溶液は塩基性になったことも分かりました。
次にカルシウムの実験です。



カルシウムの単体も常温の水に溶け、水素を発生します。
溶けた水溶液は水酸化カルシウム水溶液で、塩基性であることが分かります。
また、この水溶液のことを石灰水といい、呼気を吹き込むと白濁することが分かります。
さらに呼気を吹き込んでいくと、炭酸水素カルシウムという水溶性の塩を生じるため、生じた沈殿が消え、無色の溶液に変化します。
が、完全に消えるところまでは時間の都合で確認できませんでした。
次回の実験では別の金属の性質を確認しますので、ご期待ください。