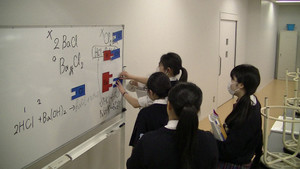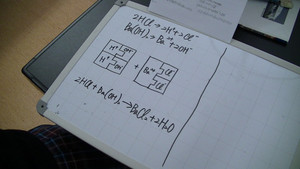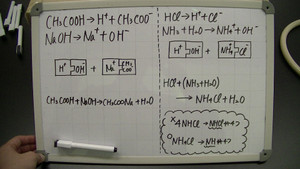共立二中高の自然がいっぱい2 (87)
2016年6月21日
梅雨に入り湿度の高い日が続いています。
今年の梅雨は降水量が少なく、6月なのに水不足になっています。
でも、学校内の雑草たちは日に日に大きくなり、気づけば背の高い雑草だらけ。
畑では作物よりもその周りにある雑草のほうが成長がよく、何を育てているのかわからないぐらいです。
ネジバナ
芝生の中からひょっこり顔を出す、そんな緑とピンクの色合いが梅雨のうっとうしさを吹き飛ばしてくれます。
ナツツバキ
毎日新しい花が次々と咲き出します。
でもその花は1日で散ってしまいます。
だから木の下にも毎日たくさんの花が落ちています。
それも楽しみのひとつです。
雨の日の葉
雨は人間にとって嫌なもの。
でも植物たちにとっては命をつなぐ大切な恵となります。
そのように見ると葉についた雨粒も一味違って見えます。
ホタルブクロ
ホタルが出るこの季節にこの花がたくさん咲き出します。
学校内のビオトープでは今年も数は少なかったですがホタルが出ました。
そしてその周りにはたくさんのこの花が咲いています。